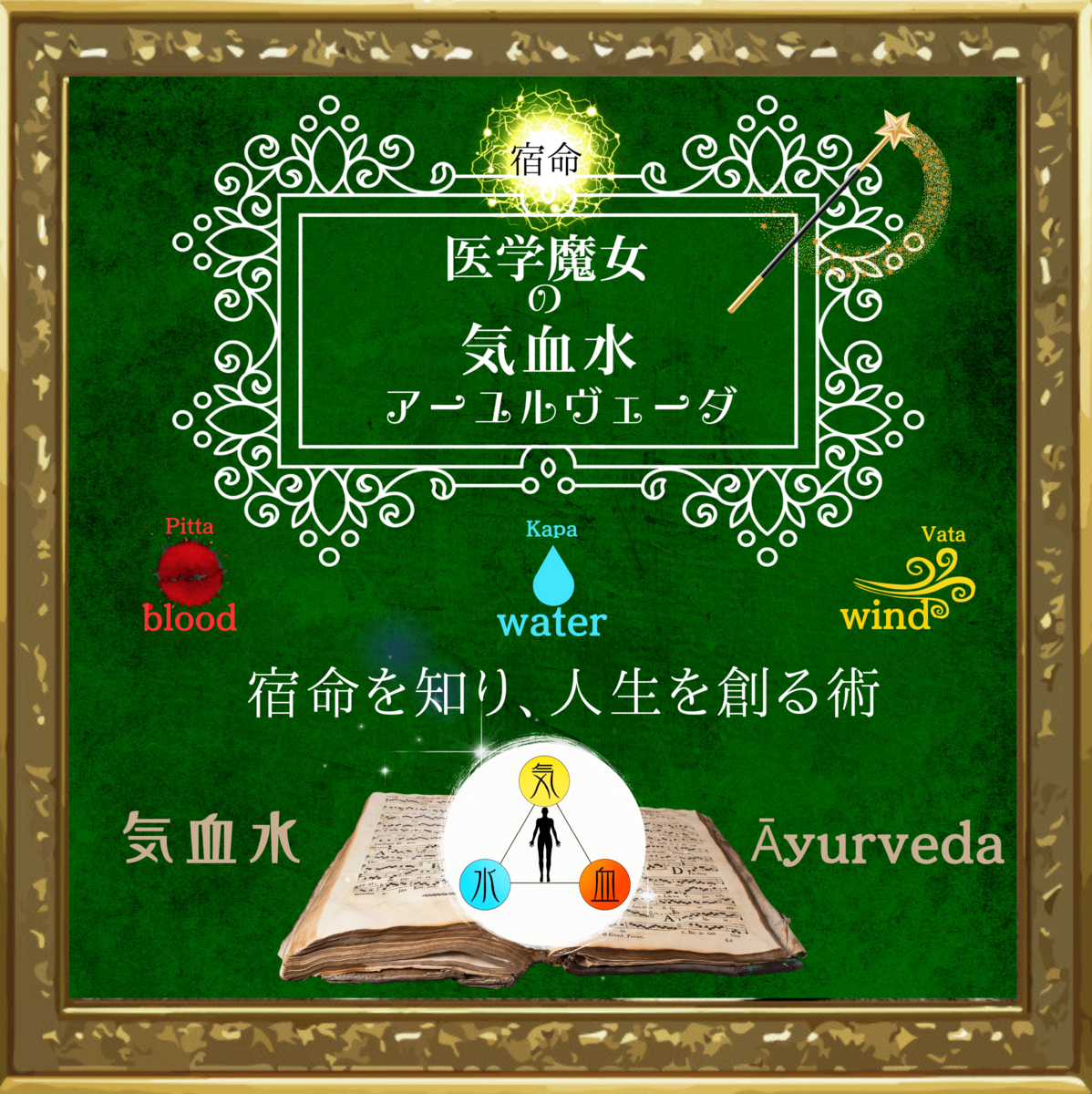ブルームRyokoです✨
大寒なので味噌づくり記事が続きます!
よくわからない画像になりましたが 笑
今日は
最高級素材のセレブ味噌✨
のレシピ大公開です✨
え?いったい何がセレブなの?
まろやかさ🌸
です!
それもそのはず、
紅こうじ塩×紅こうじ米
を使っているからです。
そう、大豆の他にお米を入れるんです!
発酵食品のオンパレードは、
よりまろやかさとコクを生み出しますよ✨
☆
愛に満ちあふれた人生で、
好きな表現をしながら生きていく
実はそれって
”ずるい女”ほどあっさり叶っていき、
真面目さんほど遠回りしてしまいます
「ちょい悪ずるい魔女」
この言葉にワクッ✨としたそこのあなた
ようこそ、ちょっと怪しげな魔法の世界へ
ポチッと▼
魔女Ryokoの正体がわかるよ🧙♀️
☆
5種類の甘み、塩味、まろやかさなどは
以下でお伝えしています。
今日はその中でダントツの1位、
甘み、塩味、まろやかさ、香り、
すべてにおいて群を抜いたお味噌です!

下の段の左から2番目、
一番左がよくある味噌の色だとすると、
少し濃いめの色のになります。
紅こうじ米の赤い色が出ているんでしょうね。
紅こうじとは

米こうじに紅こうじ菌を合わせて
発酵させたものです。
紅こうじ菌が発酵が難しいため、
手間がかかるとのことから高価です。
”紅こうじ”という名前のとおり、
赤いキレイな色が特徴です。
最近はサプリや味噌としても人気が高く、
主に血流改善やアンチエイジングで
注目されており、中国では漢方薬として
処方されているほどです。
薬膳的な効能は、以下です。
☆補気(元気やパワーを補う)
☆消食(消化促進)
☆活血(滞りやすい血流を改善、促進)
☆化於(ドロドロになった血液や塊を溶かす)
特に動脈硬化、コレステロール抑制、
食べ過ぎによる消化不良によいと
されています。
ここで薬膳 体質診断講座を受けられた方は
ピン!と来られたと思います。
そうです、気・血・水の体質別だと
血のタイプに特におすすめですね(*^-^*)
他にも黒豆を使って
さらなるアンチエイジング効果を狙った
「黒豆 × 紅こうじ × 紅こうじ塩バージョン」
をこのブログで紹介しています(^o^)▼
材料
大豆1:生米こうじ2:紅こうじ塩0.5:紅こうじ米0.1の割合です
今回は完成3kgで作りました。
大豆650g:生米こうじ1300g:紅こうじ塩325g:紅こうじ米65gです。
購入先
大豆
北海道産のとよまさりを使いました。
おだやかな甘みが特徴です。
紅こうじ米
白米に紅こうじ菌をまぶしたものです。
余ったら白米に1割ほど混ぜて炊いても。
ほんのりピンクのご飯になりますよ。
紅こうじ塩
紅こうじ菌と天然塩を合わせたものです。
そのまま使ってもまろやかで美味しい!
生米こうじ
乾燥ではなく、生のほうが味わい深いです。
保存は冷蔵庫で早めに使いましょう。

用意するもの

今回はタッパーウェアのハンドルコンテナー
を用意。密着性が高いので、保存食作りに便利。

ホワイトリカーを染み込ませたキッチンペーパー
で容器の中を拭き、消毒します。もちろん麹や
大豆を手で触る時もその度消毒しましょう。
セレブ味噌の作りかた

①たっぷりの水で透明になるまで3~4回洗う
その後、大豆の3倍の水に18時間以上
つけておく。約3倍の大きさにふくらみますよ。

②大豆を煮る
圧力鍋or鍋で3時間ほど。親指と小指で
つまんだら、軽くつぶれるぐらいまで
やわらかく煮る。
圧力鍋だと早くできますが、去年は
フタを開ける時に圧で大豆が飛び出てきて、
あわや大惨事!
ちょっと恐くなったので、
今年はたっぷり長時間できる鍋にしました。
アクが出てくるので、すくいましょう。

③紅こうじ米を炊く
紅こうじ米だけ炊飯器で炊きます。
大豆と一緒に煮る方法もあるのですが、
大豆を煮る時間が長いので紅こうじ米が
ベチャベチャになる可能性があるので、
私は別に炊いています。
今回は黒豆 × 紅こうじ米 × 紅こうじ塩味噌も
一緒に作りました。まとめてつくると効率よくて
いいですよ☆

③紅こうじ塩をまぶす
ほんのりピンクのかわいい塩です♡
米こうじを丁寧にほぐし、紅こうじ塩を
しっかり均一にまぶしていきます。
大きめのケースがあればいいですが、
なければポリ袋でやったほうがうまく
混ざり、ラクなのでおすすめです。

⑤大豆がゆであがったら煮汁をザルでこし、ケースに入れる
この時、煮汁は捨てずに取っておいてください。
大豆が固く感じた時に使います。


⑥茹で上がった大豆と③の紅こうじ米と混ぜ、マッシャー or 足でつぶす
個人的にはマッシャーより足のほうが
ラクでした。細かくつぶせるし、
後から麹と塩を混ぜるのもラクでしたよ。
ポリ袋は二重にしたほうが◎
これで、もし破けても安心☆

⑦あらかじめ混ぜておいた紅こうじ塩と米こうじと⑥をしっかり混ぜ、ボール状に固める
ポリ袋の中でしっかりまんべんなく
混ぜ合わせたらボールのように丸く、
空気をギュッギュッと抜きながら丸めてます。
ポロポロしてボールになりにくい時は、
大豆の煮汁で調節しましょう。
次は力いっぱい投げる!中の空気を抜くためです。
日頃のうっぷんを思いっきりぶつけてみましょう!!

⑧しっかり空気を抜いて密着させる。表面を平にしたら、塩を振る
できるだけ平らに。隙間や凹凸から
カビやすくなります。
塩は端までまんべんなく。やはり塩が
足りなくてもそこからカビてきます。

⑨カビとり防止の仕上げ
1.側面もキッチンペーパーにホワイトリカーを
含ませたもので拭いていきます

2.キッチンペーパーにホワイトリカーを
湿らすぐらいに含ませたものを表面に
しっかりとかぶせます。
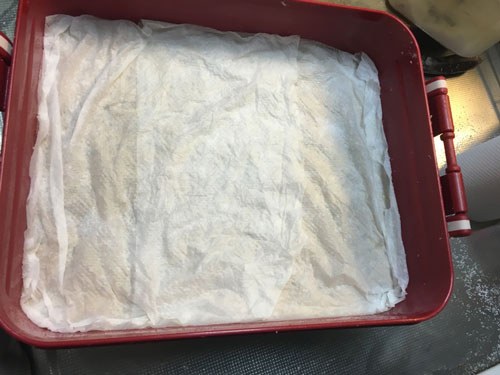

3.ラップの上にチューブわさびをのせます。
殺菌作用があり、カビ防止に効果的☆
しっかりフタをして終了です!
☆☆☆
工程はむずかしくないです、
一般的な大豆の味噌に炊いた
紅こうじ米をプラスするぐらい。
ポイントとしては
とにかく空気を抜いてしっかり詰めること、
⑨の仕上げをしっかりすれば大丈夫。
ベストな保管場所は床下ですが、
風通しがほどほどよい場所で
あればいいでしょう。
また出来上がりに多少カビが生えてても
そこだけ取り除けば大丈夫ですよ。
最高級素材をつかったセレブ味噌、
ぜひ作ってみてくださいね♪
★ブルームRyoko★
魔女ブルームRyokoのメルマガ★
医学魔女からマニアックな現実創造のお話まで✨
★LINE登録はこちらから★
魔女暦サバト、新月満月エスバット、お得情報をお知らせ✨
★YouTubeチャンネルはこちらから★
医学魔女からマニアックな現実創造のお話まで✨
★インスタグラム★
医学魔女からマニアックな現実創造のお話まで✨
【魔女ブルームSHOP】
【医学魔女の気血水アーユルヴェーダ】
カラダは小宇宙、しくみを知れば現実創造できる
【魔女の鑑定書】
あなたの中に眠る魔女性シークレットの魔法
【陰陽五行の自己実現術🔯】
魂の記憶、それは陰陽五行でこの世界の仕組みを知ることから✨
【ハーブ魔女の気血水アロマレッスン🌿】
アロマ有資格者さんのお悩みを医学魔女が解決!✨
【月経血の魔法術★マジカルボックス】
フェムケアから辿り着いた女性にしかできない圧倒的な魔術✨
【魔女ブルームの魔法ショップ】
ようこそ、魔法の世界へ。医学魔女の魔法をどうぞ✨